【開催レポート】「社会的孤立回復支援研究センター(SIRC)キックオフ・シンポジウム」
2022年7月2日、社会的孤立回復支援研究センター(SIRC)は、犯罪学研究センター(CrimRC)との共催、一般社団法人刑事司法未来の協力で、「キックオフ・シンポジウム『孤立と社会-悲しみや不安を口にできる社会を-』」を本学深草キャンパス成就館メインシアターで開催し、約40名が参加しました。
【龍谷大学ホームページ】https://www.ryukoku.ac.jp/nc/news/entry-10886.html
【EVENT概要】https://www.ryukoku.ac.jp/nc/event/entry-10494.html
【YouTube・記録映像フルバージョン(期間限定)】https://youtu.be/-2O7J9i6Qpc
【YouTube・記録映像ショートバージョン】https://youtu.be/oCbnl5DSUYc
はじめに、黒川雅代子センター長(本学短期大学部教授)が、開会のあいさつに立ち、プログラムを説明しました。次に、入澤崇学長より、学長あいさつが行われました。

「コロナ禍で学生同士のコミュニケーションが、とりにくくなっているのが現状である。龍谷大学では、『仏教SDGs』という取り組みを行っており、学生は、今自分にできることを考え、アイデアを出し合いながら実践している。卒業生のなかにも、孤立を深めている学生に対して、何かできることはないだろうかと、申し出てくれた人がいる。開学以来これまで龍谷大学は、様々な困難に直面し、乗り越えてきた。新型コロナウイルス感染症によって生じた困難もまた乗り越えなければならない。私たちは手を取り合って、生きる上で『本当に何が大切か』を自分自身に常に問いかけながら、前に進んでいく必要がある。本センターの取り組みは、まさにこのような困難や課題解決に資することができると大いに期待している。」と述べました。
次に、課題共有型円卓会議“えんたく” の話題提供として、認定NPO法人Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)副代表でフォトジャーナリストの安田菜津紀氏から「『不安を口にしていいよ』といえる社会」というテーマでお話をいただきました。安田氏は、ウクライナや東日本大震災の記録、取材を行ったご経験をもとに、次のようにお話されました。

「ウクライナからポーランドへ避難したある一家と出会った。ロシア軍によるウクライナ侵攻は、家族の分断をも引き起こしていること、そこから『放っておけない人』への支援の重要性に気がついた。また、過去にはナチスドイツによる政策によって、少数民族ロマの人々の多くが犠牲になったが、ロマへの差別は、いまもなお解消されておらず、差別や迫害されていることを受け、これらの人々にも、『困りごとをもっと言ってもよい』と伝えること、さらに支援者たちが先回りをして支援する必要性がある。」と述べられました。
つづいて、東日本大震災ではご親族を亡くされたご経験や、被災地の取材中に出会った子どもの話に触れながら、当時被災者に向けられていた「頑張れ」という言葉は、ときに相手を追い詰めてしまう可能性があることを指摘されました。そして、これまで取材を継続されている、ある被災者家族について次のようにお話されました。
「震災直後に出会った頃は仮設住宅に住まわれていたものの、その後も経済的な理由等により自宅を再建することができないでいた。最初に住んだ仮設住宅が取り壊しになり、他の仮設住宅に移動、一昨年前、災害公営住宅に引っ越された。複数回の引っ越しのたびにコミュニティが変化した。コミュニティの変化は孤立のきっかけとなり得る。お子さんは、震災時に友人を亡くしたが、これまで弱音を言わない子だった。震災から10年近く経過したとき、『自分たちよりも大変な人がいる、だから弱音は吐いてはならないと我慢してきた』と、涙を流しながら、ようやく心のうちをこぼした。これまで自分は、『言いたいことある?不安なことある?』と十分に聞くことができていたであろうか、と自身に問いかけた。」と述べられました。そして、自分にどんな役割が果たせるのかを考えること、また「不安を口にしていいよと伝える」というアプローチが大切であるとして、話題提供を終えました。
安田氏の話題提供を受け、センターテーブルのメンバーが、それぞれの知見や経験に基づいた「事実」をお話されました。司会進行は、中根真教授(本学短期大学部・子育て家庭ユニット長)がつとめました。なお、ここでの発言は、ファシリテーショングラフィックとして、暮井真絵子氏(本センターリサーチアシスタント・本学非常勤講師)がメモ共有サイトにまとめ、会場内で共有しました。

まず、本センター「ヘイトクライム」ユニット長の金尚均教授(本学法学部)は、「自分の不安を語って良い」という言葉は、実はとても重い言葉であるとしながら、ご自身のルーツに関連して、次のように述べました。「自分自身がコリアンであることを語るのが怖くて仕方がなかった。日本に生きていても良いのだろうか、社会や人が受け止めてくれるだろうかと不安だった。しかし、ある日学生が、自身のルーツについて話してくれた。勇気が必要だったと思うが、安心感を持って私に語ってくれた。それが安田氏のいうところの「不安を口にしてもよい」場なのだと思う。日本国憲法は、『国民』が前提になっている。では、国民でない人は、不平等でも良いのか。日本では、これほどの不平等が前提としてある。『社会のメンバーになれない人たち』に対して、『不安を語って良い』ということを言える場、言える人たちをどうやって増やすか、ということが課題なのではないか」と述べました。

次に、加藤武士氏(木津川ダルク代表・本学非常勤講師)は、「復興に向けた『頑張れ』というメッセージに対し、被災者は、頑張らなくて良い、被災していない人たちが頑張れば良いのでは、と疑問に思っていた。」また、「私は、里親に育てられた経験があり、大人を気遣う子どもの気持ちを知っている。子ども時代、家庭ではタブーとされる話題や、家族との間に葛藤があった。」として、自身の幼少期の経験や当時の気持ちを振り返りました。さらに、薬物依存からの回復支援活動を通して、「薬物依存症の回復者たちの笑顔は、なかなか見ることができない。『やってはならないことをやった人たち』は、笑顔を見せてはならないのだろうか。そういう社会の雰囲気こそが、回復を阻んでいる。嗜癖・嗜虐行動をとる人は、トラウマや不安を抱えていることが多い。そうした人から、ただ薬物やアルコールなどを取り上げるのではなく、抱えている不安や困りごとを聞いてあげる、寄り添える地域や社会にしていくことが重要である。」と指摘しました。

そして、竹迫生翔氏(本学法学部学生・本学中央執行委員会委員長)は、学生の立場と、学生の自治を担う立場の両方から、次のように述べました。「コロナ禍で大学へ来ることができず、講義はオンラインになった。ようやく、大学に来られるようになったことで、人との繋がりの大切さを思い知った。しかし、特に現3回生は、コロナ禍の中で入学を迎え、学内での繋がりの作り方を知らないばかりか、『不安を語ってもよい』と言われても、入構制限やステイホームの影響で直に語る場所すらなかった。不安を口にしたくても、人との接触ができない。コロナ対策に苦慮している大人たちを気遣い、遠慮して語ることができなかったジレンマがあった。他方、行動規制の緩和に伴い、直に語ることで、自分の気持ちが楽になるということを経験した。そこで、私たち委員会では、学生が語る場や自由に出入りできる居場所を提供している。」と述べました。そして、「『頑張れ』という言葉は、とても不思議である。たしかに頑張ることは大事だけども、それと同時に休息も大事だということを伝えていく必要がある。そして、語る場が設けられたとしても、急には話すことができないかもしれない。不安を語る前に、強ばった心をほぐす必要がある。まずは、雰囲気作りが重要である。」と指摘しました。

さいごに、「子育て関係ユニット」所属の堺恵准教授(本学短期大学部)は、母子支援施設での支援活動や研究の経験をもとに、次のように述べました。「まず、施設で生活する親子や職員を思い浮かべた。施設でのインタビュー調査のなかで『やっとゆっくり眠れるね』という子どもの一言が記憶に残っている。支援者が『不安を口にしてもよい』ことを直接伝えるだけでなく、雰囲気作りが重要である。例えば、その施設では、生活必需品が全て用意してあり、しかも新品で揃えていた。そこから、被支援者は、自分が受け入れてもらえたのだと思えたのでは。」と述べました。そして、職員は支援の一環として、親子に声をかけているが、支援者である職員は声をかけてもらえないことに気がついたこと、「頑張れ」という言葉については、反対に「頑張らなくてよい」と言われたことで苦しくなった経験がある。」と指摘しました。
つづいて設けられたシェアタイムでは、シンポジウム参加者が3人1組のグループに分かれて、それぞれ課題共有を行いました。グループ内で共有された課題は、メモ共有サイトを通じて、フロア全体に共有されました。その際に挙げられたキーワードのなかには、「頑張れ」や「支援」という言葉の意義や問題点、不安を口にする場があっても、相談の場として適切に機能しているとはいえないこと、支援者への支援の必要性、まずは孤立の実態を知るべきであることなどが示され、課題が明らかとなりました。

シェアタイムのあとは、話題提供者である安田氏とセンターテーブルの4名がそれぞれコメントを行いました。
おわりに、司会進行をつとめた中根教授は、「本日のテーマは『悲しみや不安を口にできる社会を』であるが、悲し

みや不安を『口にすることができない人』がいる。ハンディキャップがある方や認知症がある高齢者の方など『声なき声』に耳を傾ける必要がある。本日は、語るということ、語りを聞くということに対しては、関心を向けることができた。その一方で、言葉を自由に操ることのできない人の存在やその人たちの声を聞いていない、聞こうとしていないことに気がつくことができた。そこで、本シンポジウムのテーマを『悲しみや不安を表現できる社会を』と改め、ここで明らかとなった課題は、本センターの研究課題として、今後取り組んでいきたい。」と述べ、“えんたく”を終えました。
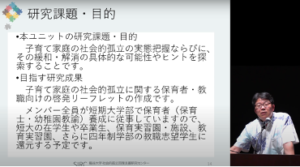
次に、本センターを構成する8つのユニットの研究課題・目的、計画等のユニット概要について、吉川悟教授(本学文学部)から「システムズアプローチ」ユニット、金尚金教授から「ヘイトクライム」ユニット、黒川雅代子教授から「グリーフサポート」ユニット、深尾昌峰教授(本学政策学部)から「“つまずき”回復エコシステム」ユニット、石塚伸一教授(本学法学部)から「ATA-net」ユニットおよび「社会的孤立理論研究」ユニット、赤津玲子准教授(本学文学部)から「関係支援」ユニット、中根真教授から「子育て家庭」ユニットの紹介がそれぞれ行われました。
各ユニットの詳細については、本センターホームページ「ユニット紹介」をご覧ください。

最後に、黒川センター長は、「社会的孤立というキーワードのもと、研究領域を超えて、英知を集約する基盤となるセンターができたことは、貴重なことである。皆様のご協力を得て、社会的孤立という課題に取り組んでいきたい。」と述べ、本シンポジウムの閉会のあいさつとしました。
